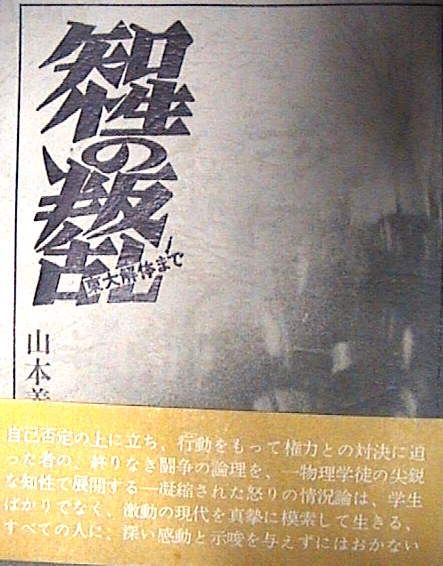 |
|
攻撃的知性の復権 一研究者としての発言 山本義隆 一九六九年一月十八〜十九日のいわゆる「安田講堂攻防戦」を頂点として、東大闘争は新しい段階にはいって今日を迎えている。山本義隆は東大全共闘議長として知られているが、「議長」というのは全共闘の性格上便宜的なものであり、正式な役職名ではない。 いま、東大闘争はこれからなのだという実感がいよいよ深まっていくのに、さまざまな罪名で公安から追及されて最前線へ出られないことにいらだちをおぼえる。町町にこれほど私服の目が光っていることをいままで気づかずにいた。なるほど日本には議会主義の秩序はあるが、それは枠外での警察国家状況で補完されているのだということが肌身に感じられる。 しかし、いまは語らねばならぬことがあまりにも多くて、言葉のまずしさにもどかしさを感ずる。すべてを語りつくせぬときは、一人の人間の実感を述べるしかない。 いままでぼくたちは先へ進むためにのみ過去を理解した。 論理に忠実であることは遠くまでゆくことを強制する。 一月十八日、十九日もまた物事の始まりでしかない。東大闘争はそういった軌跡をもつ。そのなかでぼく自身が何を考えてきたのかを書くことは、虚像につつまれてぼくたちも当初十分意識し得なかった東大闘争の一側面をあきらかにするであろう。 学長カンヅメ 学生諸君!大学院生・研究者・職員・東大の全構成員諸君!! 時計台を見よ! その内部において今や東大の醜部にせまる一群のエネルギーがうずまいている。 一昨日夕方出された三人の停学を含む多数の学生の処分の撤回を求め、我々は昨日午後二時以来すでに二十時間近くにわたり学長に回答を求めている。それに対して学長は頑強に拒否している。一体これは何を意味するのか。そしてまた、あの大量の処分は何を意味するのか。五月、池田内閣が大学管理法の問題を提起して以来、多くの学生は、それを単に大学のみの問題としてではなく、社会全体の問題としてとらえ、反対に立ち上った。(略)一方その過程に於て−今さら言うまでもない−教授会はその無能性、否、犯罪性をもわれわれに示してきた。 その事実に対する一片の反省もなく、単に規則に違反するという全くの形式的名目で処分を出した。一体教授会、評議会にわれわれ学生の運動を批判審判する権限があるだろうか。 また、被告が一言の釈明も、一言の弁護もみとめられぬ裁判があるだろうか。これこそ、大管法の大学内部における縮小再生産でなくしてなんであろうか。正に大学内部から大学の自治を破壊するものではないか。 われわれは、以上の様な見地から処分を白紙にもどし、話し合うことを求め、茅学長に会見を申し込んでいる。にもかかわらず、すでに二十時間にわたり一言の弁明も得られない。 これは学長みずから、学長の義務、責任を放棄したものと認めざるを得ない。かつ学長の今までの言動からみれば、もはや学長は大学の自治を守り、大管法に反対する意志はないとしか思われない。われわれはわれわれの正当な理由をもって、ここに、学長に対し処分撤回を要求し、会見している。 時計台をわれわれの手にとりかえせ! 再度宣言する。 われわれは不当な処分がわれわれ全体にかけられたものとみて、 あくまで処分撤回を要求する! 全東大の諸君! 時計台に結集せよ! 一九六二・十ニ・二 東大中央委員会 いま読んでも新鮮なこのビラを残して、ぼくたちは敗北の過程をたどった。すでに問題は出つくしていた。ぼくたちが敗北したのは、ヘルメットやゲバ棒やバリケードを持たなかったからではもちろんない。むしろそれらを持てるだけの、問題の根底的な認識と普遍化された思想がなかったからだ。 そしてぼく自身が、真に大学の腐敗の根源を部分的にもつきとめるのには数年問の東大内での、学生としての、研究者としての生活が必要であった。また闘いが外面化されるには羽田以降の学生運動が不可欠であった。いま助手や大学院生や医局員として東大闘争を中心的に闘っている者の多くは当時の被処分者であり、先進的に闘って敗北を経験したものである。教授たちは何一つ進歩しなかったが。 略 このように自立した思考の放棄と全社会的な価値判断の停止が、いまでは「学問の政治的中立」として学問する人の脱イデオロギー現象を進めているが、そういった非政治的日常性がきわめて犯罪的日常性であることが東大闘争で暴露された。 「大学の自治」はまた排他的に保たれている。一月二十日前後の京大の事態がそれをなによりも明らかにした。日大全共闘七百人がやってくると聞いた研究者の多くは、京大構内を逆封鎖したと聞く。デマゴギーによる大衆操作もさることながら、なぜ日大全共闘がきてはいけないのかが考えられたであろうか。 略 青年医師の自己変革 一九六二年十二月二十五日の総長室占拠と、その後の二次処分撤回闘争は敗北過程であった。だが昨年三月十二日の処分発表と七月二日の本部封鎖、講堂解放の闘いは、より巨大な闘いの出発点となった。その闘いは大管法闘争の総決算にとどまらず、はるかに先へ進展した。 だがそれに至るまでには、研究者としての数年問の思考、安保・大管法・日韓を闘った者の、自己と大学と研究が何であるかの問い返しが必要とされた。東大闘争が始ったときに闘いの論理を確立していたのでもない。それは組織論、科学者運動論、大学の研究の位置づけといった問題だけでなく、安保闘争に参加したことと、いま大学で研究していることがどう論理的に結びつくのか、結びつかないのかという問題、ヴェトナム戦争に反対することと、ぼくが素粒子論の論文を書くことがどう統一されるのか、されないのか、等々の問題であった。 思考はつねに堂々めぐりする。または結論をひきのばす。いくらかでも思考が進展したのは、闘争に飛びこんでゆき、現実の攻撃や矛盾に一つ一つ対処し、決断してゆくなかでしかなかった。 もちろん大学当局のように「状況におし流された」り、「短絡反応的に」決断したりしたわけでは決してない。 一つ一つの決断は、それに前後する長々と続く討論と総括をふまえて行動に参加する者の意思一致ではじめて可能であった。安田講堂を解放したり、研究室を封鎖することはもちろん、ヘルメットをかぶること、ゲバ棒を持つこと、実際にゲバ棒をふるうことといった、傍観者には単なるエスカレーションにしか見えないこうしたことも、論理を一つ一つ普遍化することを通じてはじめて可能となった。そのことは同時に、自己も、弾劾の対象である東大の一成員であり、一研究者であるかぎり、一歩一歩自己の存在を検証し、自らに批判を加え、普遍的な立場に身をおいてゆくことを強制した。一つ一つの決断は自分でもごまかしていたことをより鋭くえぐり出し、決着をつけさせ、原則的にしてゆく過程である。 余談になるが、一つのデモにゲバ棒を持つか持たぬか決めるのにさえ、数時間の議論を必要としたぼくたちのゲバルトは、従って「正当防衛」などというブルジョア・イデオロギーに裏づけられていたのではない。「正当防衛」こそは自己の存在のあり方を全面的に肯定した言葉であり、かかる暴力は意識の日常性に依拠してなされるものだからである。 また教授たちは「恥も外聞もすてて」と言ってシュプレヒコールをしたが、ぼくたちは誇りと自信をもって武装した。恥や誇りは行動様式ではなく、行動を支えている思想にあることを教授たちは無意識のうちに吐露したのであった。 青医通運動は研究者の闘いの一つの指標をつくった。戦後長く続いたインターン闘争は卒業医局の待遇改善運動としてはじまった。いかなる職域でもそうであるが、とりわけ失敗の許されない医療では、大学卒業後の研修は不可欠である。さらに現代社会において、医療が社会的なものである限り、医師の初期修練は社会的に保障されていなければならない。しかも技術は実践を通じて習得し得るものであり、卒後研修は医療労働を通じてしか獲得し得ない。とすれば、医学生、研修医は、医師たらんとする者の義務として卒後研修を行なわなければならないことはもちろん、それの保障を要求する権利もまた当然のことながらもっている。 しかしインターン制度の実態は、次のようなものであった。 「教育要員の準備や研修者の待遇などを準備することなしに行なわれたわが国のインターン制度は、社会が権利だけを行使して、その義務を怠った形態であり、ために青年医師の人権を侵害した形でおこなわれてきたことは疑う余地がない。しかもこれは国家権力を背景としておこなわれてきたことも事実である」(東大医学部基礎・病院連合実行委員会『医学部闘争の本質について』一九六八年八月五日)。 つまりイソターン闘争は青年医師の 「人権侵害」と「教育の名による医療労働の収奪」に対する闘いであった。 実際イソターンのみならず医局こそ「人権侵害」と「労働収奪」の場である。医局員は無給でボス教授の医療労働と研究労働の下請けをさせられ、また縄張り病院への強制出張要員にさせられた。教授は暴力手配師にあたる。驚いたことに東大病院にはこのような無給医局員が千数百人いる。 だが「人権侵害」と「労働収奪」だけでは普遍性をもち得ず、勤労大衆と連帯しうる条件にはならない。そういった人権侵害に耐えることにより、将来博士号をとることによってつぐなわれているからだ。とすれば「医師たらんとする者」にとってのみ「当然の」要求しか出てこない。各人が即自的要求を並べたてても連帯はかちとれない。事実六〇年の安保闘争の後、全国各地で闘われた病院ストの際、医局員たちは「白衣の暴力団」として看護婦さんたち医療労働老に敵対し、スト破りを働いた。 これを通して青年医師の自己批判が始る。 いままでの、医師になることを前提とした闘いの限界は何か。医師とは何か。どの社会でも「医師」は「聖職」とされている。だが、資本主義社会で公害や労災で傷ついた労働者をいやして収奪の場へ返す仕事は崇高などころか、社会の矛盾を隠蔽するだけではないか。人間を真に救ったことにはならない。 医学生がここまで認識を深化させたとき、結論は現在の医療行政のなかで国家試験を受け、博士号をとることを拒否することであった。 いま医療そのものが収奪の対象となっている。イソターン制度廃止にともなって登場した医師法一部改悪は、青年医師を国公立大病院に低賃金でクギづけにし、医療労働力を確保する。看護婦さんに対する労働強化は人間性までを無視したものであり、同時に患者に対する医療サービスの低下をきたしている。 このようにして大病院独立採算制が貫徹され、病院も(大学病院も) 差額ベッドなどを導入して営利事業化に努めている。同時に本年度予定の国民健康保険の抜本改悪は受益者負担原則の名のもとに勤労大衆からより多く医療経費を収奪する。また大学病院の教授も製薬資本と結びついて、必要以上に高価な薬を投入する。さらに大病院中心主義は、ただでさえかたよっている医療分布をよりひどくさせる。ブルジョア社会ですら営利事業たり得ないはずの医療が、国家の医療経費軽減のための金もうけの手段とされているのだ。ぼくたちはこの事実をさして医療の帝国主義的再編と言った。 青年医師たちは、現医療行政のなかで、医師たることを体制から拒絶されることを賭けてまで闘い続けること、このことを通じてはじめて普遍的な立場に立ち得るとの結論に達し、そのうえでなおかつ医療を実践せんとした。 連帯した人たち こうした闘いに、同じ大学の研究者として連帯し得たのは、自己の存在に対する学生の告発を受けとめた者のみであった。八月二十九日、全共闘が医学部本館を封鎖したとき、そこで働いていた基礎医学の若手研究者は、ほぼ次のように語った。 「学生諸君の手で半ば暴力的に研究活動を阻止されたのは腹の立つことだ。しかし一月二十九日以来すでに研究の条件はなかった。にもかかわらずわれわれが研究を続けていたのは、主体性がなかったからである。無関心に研究を続けることにより学生諸君の闘いに敵対していたことがより責められるべきである」。そして十月十七日、次のような「封鎖闘争宣言」を出して無期限スト、研究室封鎖自主管理へと決起した。 ・…医学部本館封鎖闘争に始まる一連の研究室および医局 封鎖闘争は、医学部中間層のこれまでの日常性の夢を破るも のであった。この封鎖パニックを自己の内面的契機としつつ ‥・医局員及び研究者の講座制に対決する闘いの萌芽が生れ た。これまで医学部教授会が青医連運動を黙殺と強権の暴力 によって弾圧し得る権力であった基盤は、講座制により管理 運営機構があくまで安全であり得たことにある。その意味で、 医局員及び研究者が『研究の自由』の幻想の下に日常的研究 に埋没する限り、その日常性は極めて犯罪的な政治性を帯び ており、自らは講座制の奴隷として医学部教授会を支える存 在である。封鎖闘争こそ、大学権力の管理機構をマヒさせて その権力としての実態を崩壊させ、その状況の中で初めて医 局員及び研究者が、講座制を支えてきた奴隷としての自己を 拒否する契機を獲得し得たのだ。(後略) 一年近く学生の闘いを無視し、また弾圧してきたことを何一つ反省せず、「ファシズムもやらなかった」と泣言を述べた高名の教授と対比するとき、若手研究者は、荒々しく厳しい知性の復権をかちとった。同様のことは機動隊導入の後、東洋文化研究所助手有志十人の署名入りビラにも見られる。 「…:医学生諸君の闘いを孤立させてきたわれわれの精神に、 惰眠をむさぼっていた頽廃的部分の存在したことを、われわ れは否定し得ない。…われわれは…大学に生きる限りで の存在のすべてを賭けて、新たな大学自治の創出のため、可 能なあらゆる方法によって闘うべき地平にわれわれ自身を突 き出したと考える。完全な勝利は全体制の変革される日まで 実現されず、またそこに到る途上には、国家権力との、学内 権力との、あるいは反体制運動内部の官僚どもとの、熾烈な 闘いが予想されるが、われわれはこの目標を目指して力を傾 けるであろう。われわれは連帯を求めて、孤立を恐れない。 力及ばずして倒れることを辞さないが、力尽さずにくじける ことを拒否する」 教授の一言で少なくとも日の当る場所からしめ出される若手研究者にとって、封鎖や武装は、自らの研究そのものに対する根底的な批判と、自己変革をともなってはじめて可能であった。 やがてぼくたちの多くにとって帰り得る場所はバリケードの中だけになってゆく。 物理学徒として 医学部の闘いに比較して、理学部の若手研究者・大学院生がどのような思考の軌跡を残したのかは重要である。 物理教室などでは最も純化された形で問題が提起されているからだ。 物理教室の、とりわけ基礎物理学の研究室では、研究の質からしても医学部や都市工学科のように直接的に労働を収奪されているとは単純には語れない。また研究室における教授との問の人間関係もそれほど前近代的でもない。学問自体がより進歩しているため、教授の論文でも大学院生の論文でも平等に、ある程度客観的に評価され得る。まだまだひどいところもあるが、それでも物理教室は東大で最も近代化され、民主化された部類に入るだろう。では問題はないのか。否! まさにもっとも近代化されているがゆえに、当面の課題としてスローガン化され得なくとも、より本質的で重大な問題が潜んでいる。 多くの基礎物理学の研究者には、研究成果は自己の私有財産という小所有者意識が濃厚で、同時に平等でアトム化された研究者は、人間の価値までも研究成果を通じてのみ評価される。研究者はひたすら細分化された自閉領域の中にみずからを追いやり、全体的な学問像も、社会的な学問の位置も、見失ってゆく。同時に脱イデオロギー現象は極限に進み、結果として体制べったりになってゆく。論文生産競争により、物量に物を言わせた実証主義が万能視され、めぐまれた東大の研究者をより一層権威づけるとともに、冷遇された地方の研究者までがそれに追随し、独創性をなくしてゆく。こういったことがいかにして論理的に歴史的・社会的正当性をもつにいたったかが重要である。 ぼくたちは何回となくこのことを議論した。東大闘争以前も、たとえはアジア財団からの資金援助で「国際夏の学校」が行なわれたとき、北京シンポジウム、米軍資金闘争等々の機会をとらえて。東大闘争がはじまってからも、理学系大学院闘争委員会内部で。それは際限ない。 議論であった。はつかねずみがオリの中でまわっているように堂々めぐりが続いた。 「大学院生が学生の闘いに便乗するのではなく、大学院生の立場から闘うべきだ」実際、「政府ほ基礎科学に金を出さない」といって、東大の研究者に被害者意識を植えつけることでは、研究者の意識変革はかちとれず、かれらの特権を合法化するだけである。 自己検証の上に立って 極限的に進歩した近代自然科学のなかで、闘いは自己の分裂の克服からはじまる。矛盾は研究者と文部省や、研究老と研究制度の間にあるのではなく、研究者個々人内部にある。 ぼくたちは王子や三里塚の闘争に参加した。しかしデモから帰ると平和な研究室があり、研究できるというのはたまらない欺瞞である。研究室と街頭の亀裂は両者を往復しても埋められない。 では研究をやめるべきか。それは矛盾の止揚ではなく矛盾からの逃亡ではないか。徹底した批判的原理に基づいて自己の日常的存在を検証し、普遍的な認識に立ちかえる努力をすること。そうして得られた認識に従って、社会に寄生し、労働者階級に敵対している自己を否定し、そこから社会的変革を実践する。抽象的にしか語れないが結論らしいものはこうでしかない。 それは一時的にせよ研究の進歩を止めてでも闘うことを意味した。研究者として研究を放棄し、研究室を封鎖・自主管理してゆくなかで、改めて研究をトータルにとらえかえす作業が必要とされた。現在の政治的・社会的状況を考えたとき、結果として研究者たり得なくなるかもしれないが、それは別問題である。真に研究者となるためにぽくたちは研究の放棄を主張せざるを得なかった。 この結論から出てくる行動は、「なにかをかち取ったら『勝利』と総括して闘争を収める」ということには当然ならない。むしろ大学で、研究室で、そういった囲いを永続的に進めることを意味する。当然その先は安保闘争にもつながっている。「全共闘はたとえ『七項目』をのんでも闘争をやめないだろう(はじめから『七項目』を受入れる気がないのにこういうことは言えるはずがないが、それはいまは問わない)。だから民青や一般学生と手を打って紛争を収拾させる」という大学当局の論理は、冷酷な官僚の論理であり政治家の論理ではあっても、研究者の論理ではない。 こういった論理のゆきつくところは、われわれの要求にこたえることなく、機動隊を使ってでも全共闘を圧殺することである。 ぼくたちの闘いにとって、より重要なことは政治的考慮よりも闘いを貫く思想の原点である。もちろんぼくたちはマスコミの言うように「玉砕」などはしない。一人になってもやはり研究者たろうとする。ぼくも、自己否定に自己否定を重ねて最後にただの人間ー自覚した人間になって、その後あらためてやはり一物理学徒として生きてゆきたいと思う。 しかし、日本にヴェトナムを持込まないことが日本の平和を守ることではないように、研究室が戦場にならないことを願うことは「大学の自治」や「研究の自由」を守ることではなく、研究者のエゴイズムを守っているだけである。ぼくたちは研究室を戦場にしてでも闘いの圧殺には反撃する。まして攻撃が拠点に向けられたならば、何を使ってでも守り抜くであろう。知性に誠実であるためには、そうする以外に何があろう。政治家や官僚どもの論理に、ぼくたちが一年間の思考でたどりついた論理を売渡すことはできない。 覚えず、つたないことを書き散らしたが、これは東大闘争の中でジグザグしつつ歩んだ一研究者の思考の軌跡である。ぼくたちは闘争のなかで一つ一つ論理を検証し、ややもすれば日常性に回帰し論理の深化に耐えきれないぼくたち自身の弱さを自己批判しつつ、歩んだ。外に向っては告発の対象を拡大しつつ、内に向っては凝縮させていった。 東大闘争は帝国主義国家の知的中枢に位置している精神のゴミタメ的な東京大学の腐敗の中で、攻撃的知性を復権させる闘争であった。だが東京大学は告発にこたえることも出来なかった。ただ東大当局は「入試実施」を合言葉に旧秩序の復帰に狂奔し、あげくにぼくたちを国家権力に売渡した。空前の弾圧で学友を傷つけ、逮捕させ、告訴までした東大当局を、満身の怒りをこめて弾劾する。 ぼくは思う。いま東大に存在理由があるのは、それが「解体」の対象としてのみである。それにはいろいろな意味がこめられている。東大の権力機構の中での位置、九十年にわたる犯罪的・反人民的過去、それが「体制的であると「反体制的」であるとを問わず、多くの官僚どもを輩出してきたこと、教育や研究の中央集権化とゆがみを作ってきたこと等々。 しかし、一体何を第一に解体するのかと問われれば、少々とまどった後、うまく言えないが、九年間東大で学ぶ間にぼく自身がいつのまにか身につけた属性や思考様式やさまざまなもの、つまりぼく自身ではないかと答えざるを得ない。その先に、今後さらに続く闘争の中でぼく自身の社会と学問と、何よりも闘争そのものへの新しいかかわり方ができるであろう。 (一九六九年二月十日記) |
 |
「討論・68〜69年越冬宣言」1968・12・29 、、、、、 山本義隆(東大全共闘) 、、、彼らは党派として活動している限り共産主義的人間であると語るが、ぼくらはそう語り切れない。ぼくらは党派の人間として共産主義的人間であるという形で他の一切をごまかすとか、切り捨てるとかいうことができない。むしろ大学院生である、科学者であるということによってぼくらの人間が問われるのだ。松沢君のいったのもそのことだ。 ぼくら東大生、あるいは東大の大学院生、東大における研究者というところから出発して、その矛盾を解明していく。 切開していく。 そこにおいてぼくら自身の存在を否定しあらためてより普遍的な立場に立つ。 そこから東大を思想的に粉砕する対象としてしか見ざるを得なくなる。 そのことによってぼくら自身も基盤をなくしていく、結果としてルンペン・インテリになろうがしょうがないことだ。そういう意味においてしかぼくらは共産主義的人間というのは語り得ないんだ。党派人間のほうが東大を乗り切った過程で免罪符的に救われていく危険性を宿している。 |
「アエラ」 2003年9月15日 全共闘運動を記録した映画『怒りをうたえ』の上映運動をいまも続ける三浦暉(みうらあきら)さん(63)は、山本義隆について「その潔さ、運動への責任の取り方、厳しく自己の倫理を貫く姿勢に、敬意を表するしかない」 上映会は8月にも都内であり、約120人が訪れた。会場の入り口に、全共闘時代の山本氏の著書が平積みされ、ほとんど売り切れた。観客の大半は20〜30代の若者で、全共闘世代はわずか。1人は上映後、こう感想を寄せた。 「『最後の最後まで闘うぞ』と、共に叫んだ人たちは今、どこにいるのだろう」 山本氏は、その一つの答えを出している。運動のただ中にいた69年2月、当時の『朝日ジャーナル』にこう手記を寄せていた。 「ぼくも、自己否定に自己否定を重ねて最後にただの人間──自覚した人間となって、その後あらためてやはり一物理学徒として生きてゆきたいと思う」 |
大佛次郎賞' 毎日出版文化賞 第一回パピルス賞 『磁力と重力の発見』1,2,3 山本義隆著 みすず書房  書評 ●磁力と重力の発見1-3 佐々木力氏(『東京新聞』2003年6月22日) 近年の科学史書の力作として、満腔(まんこう)の賛辞を贈りたい書である。 ●磁力と重力の発見 山形浩生氏(『朝日新聞』2003年7月20日) 現代科学の成立についての(その非科学的な部分、たとえば魔法だの錬金術だのを切り捨てることで、成立したという)通念をひっくり返してくれる快著。磁力や重力という常識化した概念/現象の不思議さに、改めて読者の目を開かせてくれるだろう。 ●磁力と重力の発見 池内了氏(『信濃毎日新聞』2003年7月27日) 主として磁力概念の変遷を、古代ギリシャから中世、ルネッサンス・近代の始まりまでを克明にたどる。膨大な資料を駆使した著者の責任の勉強ぶりが偲ばれる。後に書かれた技術史の作品への鋭い批判が輝いて見える。 ●磁力と重力の発見 河本英夫氏(「化学」2003年10月) 斬新な問題設定で一貫した議論を展開した著作は、実にさまざまなことに気づかせてくれる。 ●磁力と重力の発見 浅羽雅晴氏(10月19日掲載読売新聞) 科学史の常識を破る。 久しぶりに心地よい疲労感を覚えた。かれこれ1000ページ近い分量の全巻を読了した達成感もあるが、科学史の常識を破る知的スリルの重厚な手応えを感じ取ることができたからだ。在野の物理学者によるラジカルな問題提起に、目を見開かされる思いがする。刮目(かつもく)すべき労作といえる。 |
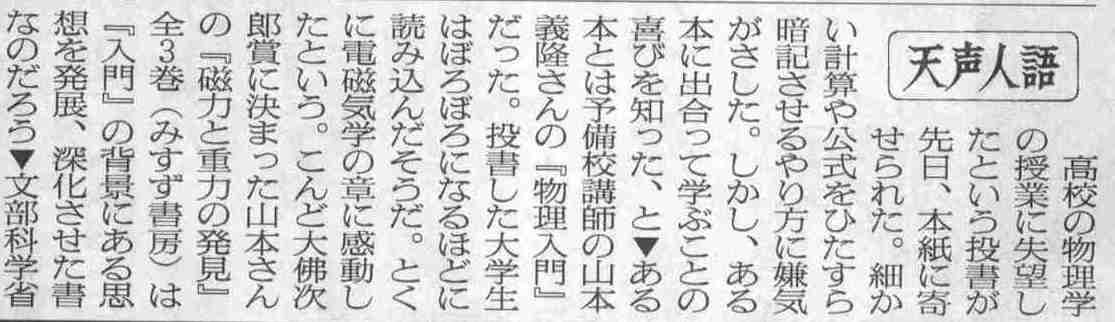 2004-1-25asahi |
『その時日本は・東大全共闘』NHK出版 、、学生の半数以上が参加したとされる東大闘争。 いったい何が学生たちをこれほどの激しい闘争へと駆り立てていったのだろうか。 一年間に及ぶ闘争の間につくられたビラやパンフレットは五〇〇〇点以上に及ぶ。その内容は、一九九四(平成六)年に国立国会図書館に寄贈された『東大闘争資料集』全二三巻で知ることができる。当時の全共闘のメンバーがつくつた「68・69を記録する会」が、仲間たちに資料提供を呼びかけ、五年がかりで分類・整理したものだ。 「封鎖、それは連帯のしるし」「ファッショ的医学部教授会を打倒せよ」「本日、沖縄闘争に決起せよ」「70年安保闘争の展望」「ベトナム討論会」「公害ゼミ」「文化大革命の勝利万歳」「ソ連のチェコ侵入事件と現代社会主義の展望」 「無期限スト、大衆団交で勝利まで闘い抜こう」…‥・。 ビラのテーマは、身近な大学の問題から世界情勢にまで及んでいる。 それは、世界と日本の戦後体制の矛盾を映し出す鐘だ。 論理や表現は稚拙であるにせよ、これから社会に出ようとする学生たちが日本と世界の問題にどれほど敏感に反応していたかが伝わってくる。、、、 全共闘代表だった山本義隆は、運動を離れてからすべてのマスコミの取材を拒絶し、現在は都内の予備校で物理を教えている。手紙で「ぜひ証言を」と取材を依頼したが、簡潔で丁重な断り状がすぐに送られてきた。断る理由は書かれていなかったが、文面かち読み取れる意志の固さと周辺情報を考慮した結果、取材は断念せざるをえなかった。 国立国会図書館に寄贈された『東大闘争資料集』 については冒頭でふれた。この資料集を中心になって編纂したのが山本だった。B5判で全二三巻、積み重ねると一メートルを超える膨大な資料集だ。赤いハードカバーで、背中に金文字で 「東大闘争資料集」と記されている (マイクロフィルム版もある)。 山本は、仲間から寄せられた数万点の資料を分類し、重複を省いて日付を確定したうえでデータベースに打ち込むという気の遠くなるような作業を、ほぼ一人で数年にわたって続けたという。全共闘側だけではなく、民青や当局側の発行文書も網羅されている。山本は、資料の完成報告の中にこう書いた。 「国会図書館に通って資料を読むという労力を厭わない限り、ドキュメントという一面ではあれ東大闘争について、意図的なねつ造や隠ペい、等々の歪曲を許すことなく、その実相に触れることが可能となったのではないでしょうか」 どんなに対象の内部に入り込んで取材したとしても、第三者が表現するものは取材される本人の意図と同じにはならない。それが彼には許せないのだろう。闘争から二六年が過ぎた現在までのところ、この資料集だけが東大闘争について彼が発した唯一のメッセージである。 |